マーケティングを学び始めると、よく目にする「戦略」と「戦術」。この2つ、実は意味も役割もまったく異なります。
戦略が方向性を示す地図だとすれば、戦術はそこへ向かうための行動プラン。どちらも欠かせませんが、混同してしまうと成果につながりません。
本記事では、初心者でも理解しやすいように「戦略と戦術の違い」から「実務での使い分け方」まで丁寧に解説します。正しい考え方を身につけ、実践で使えるマーケティングの知識を身に着けましょう。
マーケティングの戦略と戦術の違い
マーケティングの仕事において、「戦略」と「戦術」という言葉が頻繁に登場します。
しかし、これらを正しく使い分けられている人は意外と多くありません。両者は目的や役割がまったく異なるため、混同してしまうと施策がブレたり、成果につながらない原因になります。
そこでまずは、「戦略」と「戦術」の違いをマーケティングの観点から整理していきましょう。それぞれの意味を理解することで、マーケティングの精度が大きく変わります。
マーケティング戦略
マーケティング戦略とは、「どの市場で、どんな価値を、誰に届けるか」といった全体の方向性を決めることです。
ゴールまでの道筋を描く設計図のような存在で、最終的な成果を左右する基盤となります。
例えば「若年層向けに新しいヘルスケアブランドを立ち上げる」というミッションがあるとしましょう。この場合、まず市場や競合、自社の強みなどを分析した上で、どのターゲット層に・どのような価値を・どんなポジショニングで提供するかを定めていきます。ここで使われる代表的な考え方に「STP(セグメンテーション・ターゲティング・ポジショニング)」があります。
戦略は一度決めたら大きな変更はせず、中長期で一貫性を持たせることが重要です。
STPはこちらの記事で紹介しています。
マーケティング戦術
一方の戦術は、戦略で定めた方向性を実現するための具体的なアクションです。
「どうやって届けるか」「どんな手段を使うか」を決める部分で、広告やSNS、キャンペーン施策、販売チャネルの選定などがこれに該当します。
例えば、ターゲットが20代男性で「運動不足を手軽に解消したい」というニーズがある場合、「Instagramでワークアウトのショート動画を発信」「インフルエンサーとタイアップしたプロモーション」「アプリと連動したキャンペーン企画」などの戦術が考えられます。
戦術は市場環境やユーザーの反応によって柔軟に変更することが必要です。成果を見ながら最適化する姿勢が重要です。
戦略と戦術を明確に区別することで、マーケティングの成果は大きく変わります。目的地とルートが一致していなければ、いくら努力しても望む結果にはたどり着けません。まずはこの違いをしっかり理解し、実務に活かせるようにしていきましょう。
「戦略」と「戦術」は経営とマーケティングで異なる
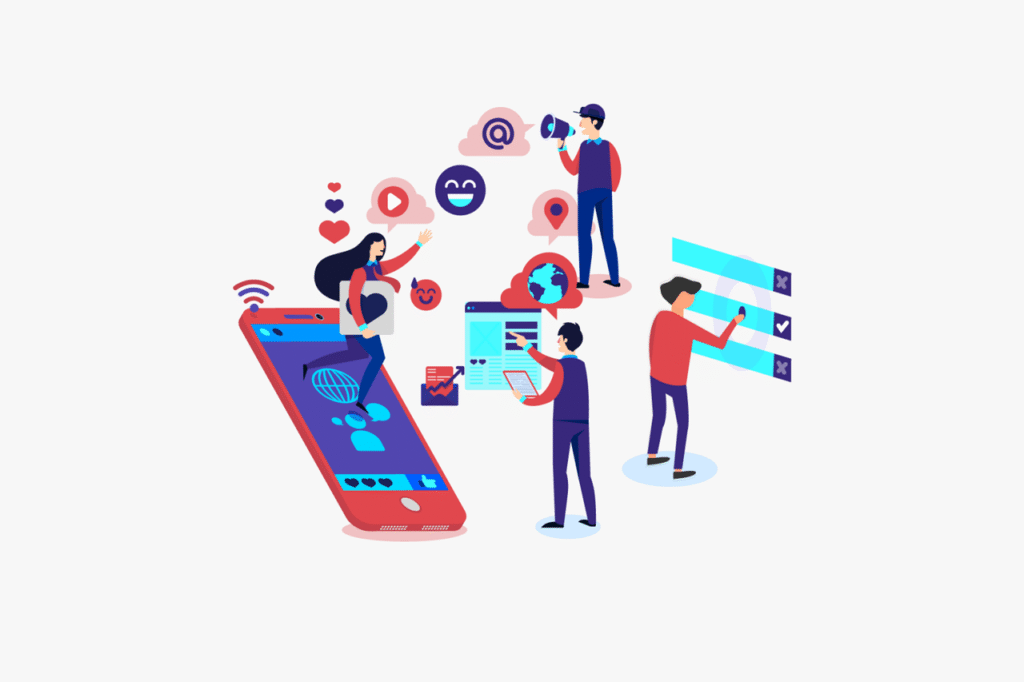
「戦略」と「戦術」は、マーケティングだけでなく経営の分野でも使われる言葉です。
ただし、それぞれの分野での使い方や意味合いには微妙な違いがあります。
この違いを理解しておくことで、業務でのコミュニケーションや意思決定がスムーズになります。
経営における戦略と戦術
経営の文脈では、戦略は会社全体の方向性を示す長期的な計画を意味する言葉です。
例えば「今後5年間でグローバル市場に進出する」「新規事業で売上の25%を構成する」といった、中長期のゴール設定が該当します。
これは会社全体のリソース配分や組織体制に大きく関わるため、トップマネジメントの意思決定によって策定されることが多いです。
一方、戦術はその戦略を実現するために、現場や部門ごとに実行される具体的な施策です。例えば、海外進出戦略を支えるために、現地法人の設立、人材採用、営業チャネルの構築といった取り組みが行われます。
経営においては、戦略が「全社レベルの目的地」、戦術が「部門ごとの進み方」と言い換えるとイメージしやすいでしょう。
マーケティングにおける戦略と戦術
マーケティングにおける戦略は、事業やブランド単位で「誰に」「何を」「どのように届けるか」を決めることです。市場分析やターゲティング、ブランドのポジショニングを通じて、顧客に提供する価値を明確にするのが特徴です。
マーケティング戦略は、部門内での意思統一や施策の軸として機能します。
一方で、戦術はその戦略を実行に移すための施策です。
例えば、SNSでのキャンペーン設計、Web広告の出稿、店頭販促物の制作など、具体的かつ短期的なアクションが中心になります。戦術はユーザーの反応を見ながら調整していく柔軟性が求められます。
つまり、経営では全社的な視点からの長期計画としての「戦略」、マーケティングでは市場との接点設計による利益増大のための「戦略」として用いられており、目的と対象スコープの違いがあるのです。
これを理解しておくと、経営層とマーケティング担当者の間でズレのない議論がしやすくなります。
マーケティング戦略を立てるポイント
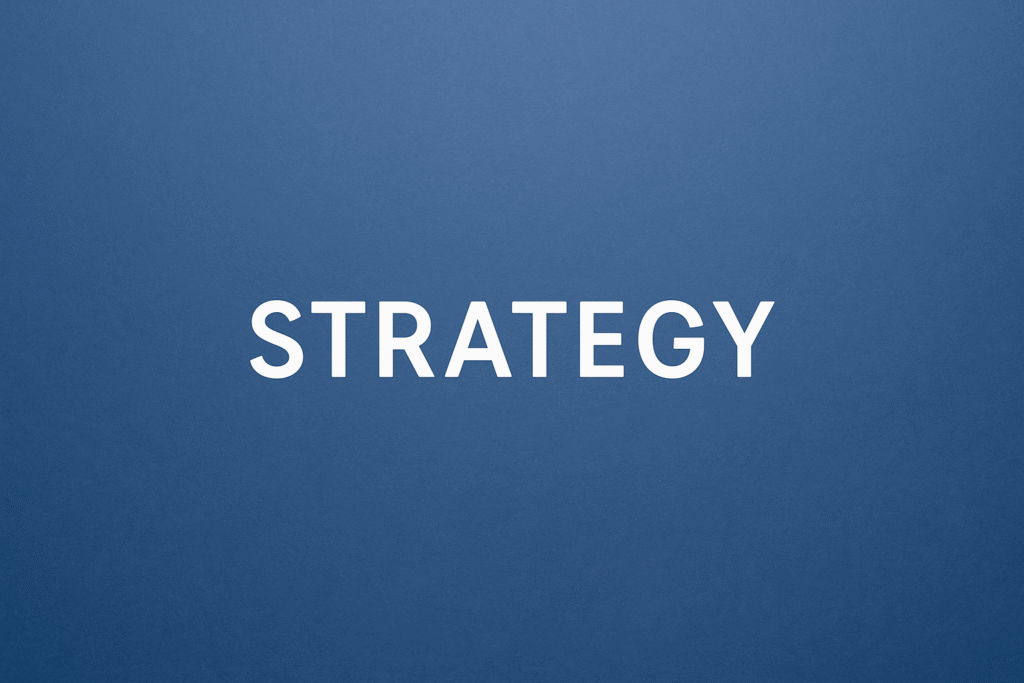
「戦略」と「戦術」の違いは分かったけど、どうやって戦略を立てて戦術を進めていくのかという方法を正しく理解しておかないと、成果につながる戦略立案や施策実行ができません。
ここではマーケティング戦略を立てるポイントを順序だてて紹介していきます。
① 現状分析と市場調査を丁寧に行う
まずは市場や競合、自社の立ち位置を把握しなければ、正しい判断はできません。
戦略設計の出発点は、自社や市場の「今」を正確に把握することです。
競合の動向、顧客のニーズ、業界の変化を客観的に調査・分析することで、的外れな戦略を防げます。
SWOTやPESTといったフレームワークも活用し、戦略の土台を固めましょう。
② 明確な目標設定と数値KPIの策定
目指すゴールが明確でなければ、施策の精度も判断の軸もブレてしまいます。
戦略には、具体的なゴールが不可欠です。
「売上〇%増」「リード数〇件」など、誰が見ても判断できるKPIを設定すると、組織内での進捗共有や改善判断がしやすいです。
曖昧な目標は判断を鈍らせ、戦術のブレにもつながります。
③ ターゲット像(ペルソナ)を具体化する
誰に届けるのかを具体化することで、伝えるべき価値が明確になります。
施策の軸となるのが、ターゲット像の明確化です。
年齢・性別・職業だけでなく、価値観や課題、日常の行動まで踏み込んだ「ペルソナ」を作ることで、伝える内容や手法がより具体的になります。
感情に響く施策を生み出すために必要です。
④ 差別化戦略とポジショニング設計
競合と似たような価値訴求では、顧客に選ばれません。
自社ならではの強みや独自性を見極め、「このブランドは〇〇な価値がある」と想起してもらえるようなポジションを設計します。
STPの中でも特にポジショニングが重要です。
⑤ フレームワークを活用した計画立案
情報整理や意思決定の質を高めるには、構造的な思考が欠かせません。
戦略を論理的に組み立てるためには、STPや3Cなどのフレームワークが役立ちます。
複雑な情報を整理しやすくなり、抜け漏れや思い込みを防げるのが利点です。関係者間の認識を揃えるうえでも、共通言語として有効です。
⑥ PDCAを回す評価・改善体制の整備
戦略は立てたら終わりではなく、改善を前提に進化させていくものです。
戦略は一度立てたら終わりではなく、実行→評価→改善を繰り返して育てていきます。
KPIに基づいた振り返りを定期的に行い、必要に応じて戦略や施策の方向を調整できる体制を整えましょう。
柔軟さと継続性が成果を生みます。
マーケティング戦術を立てるポイント

次に、マーケティング戦術を立てるポイントについて紹介します。
① 戦略に紐づく施策の設計
戦術は、戦略から逆算して設計する必要があります。
やることリストではなく、「なぜこの施策をやるのか」が説明できる設計を心がけましょう。
ただ単に思い付きの「やること」を並べても、ターゲットやポジショニングとズレた施策は効果が薄く、無駄なコストになりかねません。
戦略で描いた方向性を実現するには、どの手段が適切かを論理的に検討しましょう。
② コンテンツ施策とチャネル戦略
メッセージと接点の組み合わせ次第で、伝わり方も成果も大きく変わります。
顧客にアプローチするには、何を伝えるか(コンテンツ)と、どこで伝えるか(チャネル)の設計がカギです。
SNS、メール、広告、オウンドメディアなどチャネルの特性を理解し、ターゲットの行動パターンに合わせた設計を行います。
③ リード獲得〜育成の流れを構築
一度の集客したら終わりではなく、継続的に関係を深めていく設計が必要です。
見込み顧客(リード)を集めるだけでなく、その後の育成(ナーチャリング)までを一連の流れで設計することで、リピート顧客として継続的に製品・サービスを利用してくれます。
ホワイトペーパー配布→メール配信→個別提案など、ステップごとの体験設計が成果につながります。
④ ロイヤルティ強化の施策設計
一度の購入で終わらせず、継続的な関係を築くための仕組みづくりが重要です。
定期購入や会員限定特典、アフターフォローなどで満足度と信頼を高め、ファン化を促します。
リピーターが安定的な売上を支える基盤になります。
⑤ KPI基準で施策効果を測定・改善
施策の成果は、感覚ではなく数値で判断するようにしましょう。
「やって終わり」ではなく、「やった結果、どうだったか」が判断が重要です。
クリック率やCVR(コンバージョン率)、LTV(顧客生涯価値)などのKPIを事前に設定し、施策ごとに改善ポイントを把握できるようにします。
改善の質が、成果の差に直結します。
⑥ 柔軟なリソース配分と予算管理
限られたリソースを成果につなげるためには「選択と集中」が欠かせません。
すべての施策に均等にコストをかけるのではなく、成果や重要度に応じた優先順位づけが必要です。
PDCAの結果をもとに、費用対効果の高い施策に予算や人員を集中させることで、全体の効率と成果を高められます。
マーケティング戦略・戦術の具体例|サントリー「クラフトボス」

- 戦略設計
-
サントリーは、缶コーヒー離れに直面する若年層を対象に「缶コーヒーに代わるペットボトル飲料」を新提案。その目的は、若い層の取り込みとブランド若返りでした。
- 戦術実行
-
以下のような戦術を実施し、顧客への印象付けを行い、販売拡大を行いました。
戦術 内容 チャネルとコンテンツ SNSやテレビCMで「若者の缶コーヒー離れ」を逆手にとったブランディングを展開
「宇宙人ジョーンズ」というキャラクターを起用したキャッチーなCMが特徴商品デザインの刷新 2021年にラベル幅縮小+エンボス加工されたペットボトルにリニューアルし、開放感と手触りを強化
2024年には、利用シーンやお客様の反応を踏まえて、見た目も中身も刷新販売促進 タワーレコードやソフトバンクなど他社との連携キャンペーンを実施し、新規ユーザーを獲得 - 成果
-
発売から3年でペットボトルコーヒー市場を牽引する存在に。
ブランドとして「自然な健康価値」や「カジュアル感」を獲得しつつ、発売後もリニューアルで新訴求を加える攻めの姿勢を継続しました。
これら一連のマーケティングから以下のことが学べます。
- 戦略段階で若者の“離れ”を捉えたポジショニング設計があった
- 戦術ではパッケージも含めたブランド体験を重視したアクション設計
- 成果を受けて継続的な改善(チャネルやクリエイティブ)を繰り返している
戦略と戦術を正しく理解し、成果を出せるマーケティングをしよう!
マーケティングにおける「戦略」と「戦術」は、それぞれ目的も内容も異なります。混同してしまうと、施策がブレたり、狙った成果が出づらくなる原因になります。
本記事ではその違いを明確にし、どのように設計し、どう実行へ落とし込むのかを具体的に紹介してきました。
重要なのは、順序を守りながら論理的に設計することと、現場で柔軟に運用すること。
まずは身近なプロジェクトで「戦略と戦術を分けて考える」ことから始めてみましょう。
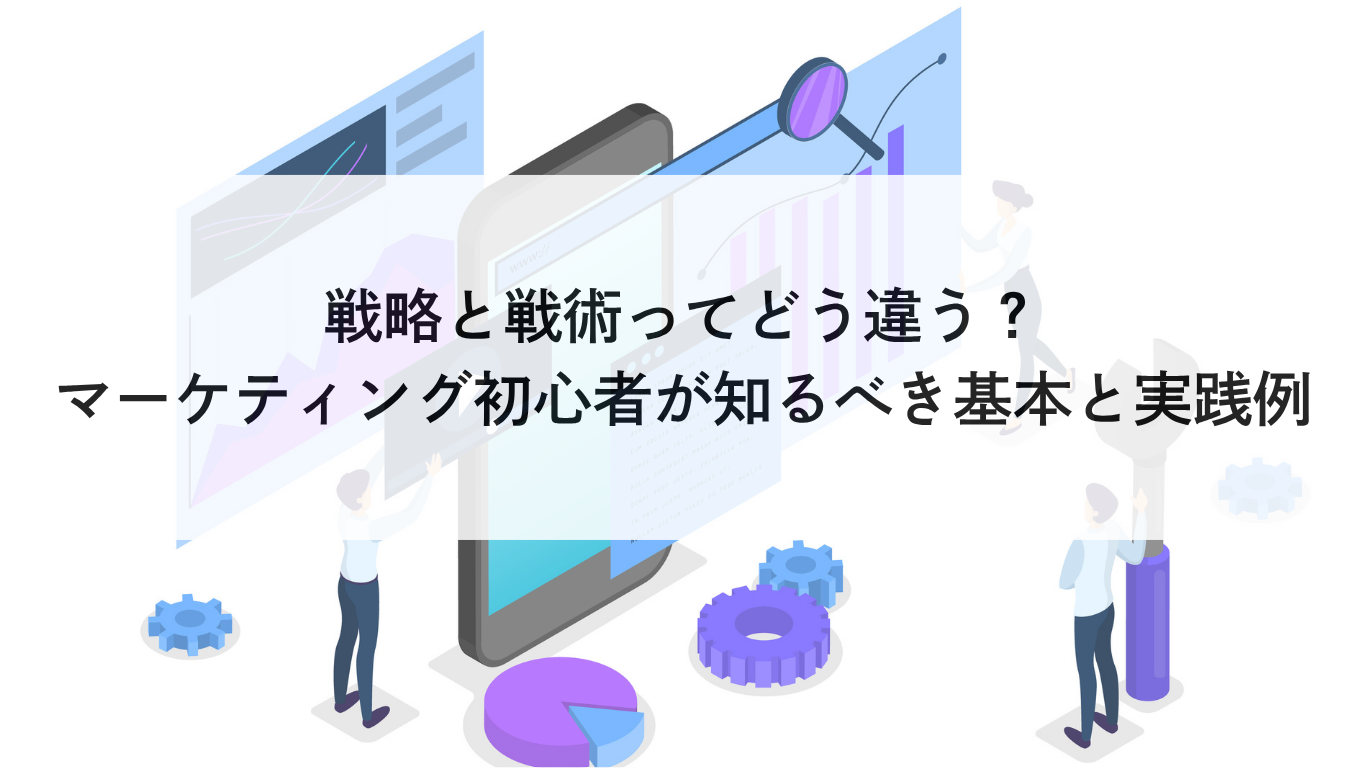
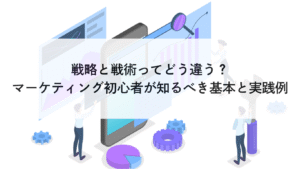
コメント